神社やお寺を参拝したときに来た思い出に御朱印をもらう方は多いと思います。
しかし、多くの方たちは御朱印の意味や頂くときのマナーは意外と知らないはず。
今回はそんな御朱印の意味やマナーを紹介していきます。
御朱印の意味とマナー

近年注目される御朱印集め。
「集め」と聞くとコレクションのような印象を受けますが、御朱印を頂くにはマナーがあります。
御朱印は日本の寺社に参拝した証として頂く神仏とのご縁の記録です。
参拝前に御朱印を頂きに行くのはマナー違反になってしまうので注意してください。
そして御朱印代を納めて御朱印を頂くときは両手で受け取りお礼を忘れないようにしてください。
御朱印帳の使い方

ここからは御朱印帳のおすすめの使い方をご紹介していきます、
表紙にご朱印帳と書く
寺社で販売されているご朱印帳は最初から印字されているものがほとんどですが市販のご朱印帳は印字されていない場合があります。
表紙にご朱印帳の印字がない場合は白紙のラベルに記入して貼りましょう。
 めめきん
めめきんそもそも御朱印帳にラベルを付ける必要はあるの?



ご朱印帳は蛇腹式のものが多く上下が分かりにくいからなんです。
名前を記入する
御朱印帳には名前を明記することをおすすめします。
似たようなデザインのご朱印帳があったときお渡しのときに取り違えが起きてしまう可能性があるためです。
名前の記入はご朱印帳の裏表紙など目立たない部分で構いません。
個人情報なので名前は書きたくないという方はご朱印帳に自分だけが分かる印をつけておくと良いでしょう。
綺麗に残すために裏面は使用しない


ご朱印帳を丁寧に扱いたい、ご朱印帳を綺麗に残したいという方は裏面を残す使い方がいいでしょう。
蛇服式の御朱印を開いたときに訪れた寺社の御朱印が1度に見られますし、裏写りしないので綺麗に保管できますよ。
とはいえ、ご朱印帳の裏面を使ってはいけないというルールはありません。
1冊に沢山の御朱印を集める使い方をしたい方はもちろん裏面を使っても構いません。
お寺・神社で使い分ける


お寺と神社で御朱印帳をわけなければいけないというルールはありませんがそれぞれ使い分けることをおすすめです。
お寺の御朱印は大判
神社は小判
貼るタイプの御朱印のサイズが大きくて周囲をカットしたことがある方もいるのではないでしょうか。
また、レアケースでありますが、神社とお寺の御朱印が混ざっていることで御朱印を断られたという話もあります。
お寺と神社の考え方を尊重し、神様と仏様が喧嘩しないようにするためにもご朱印帳は2冊用意すると良いでしょう。
記念スタンプは別のノートを用意する


御朱印と記念スタンプは別物ですので、一緒にしないように注意してください。
御朱印は参拝の証明であり、神様、仏様の分身です。
神聖なものですので記念スタンプを押すときは別のノートを用意してください。
神社仏閣によっては記念スタンプが押されていることで御朱印を断られるというケースがあります。
また、近年お城でもらえる御城印も記念品ですので一緒にしないように注意してください。
まとめ


御朱印を頂く方法、マナーをご紹介しました。
ただ御朱印を頂きに行くのではなく、神仏への敬意を払いきちんと意味を知ることで大切です。
お気に入りの御朱印帳を手に御朱印集めをしてくださいね。



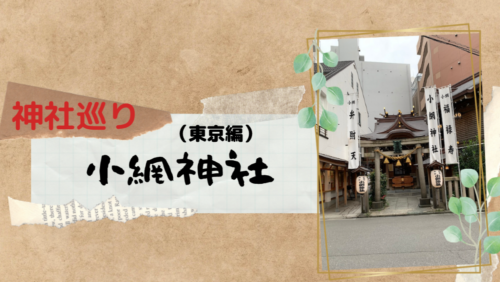
コメント